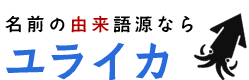【意味】
チャルメラとは、屋台の中華そば屋の宣伝に使用される笛のこと。
【語源・由来・成り立ち】
チャルメラの語源・由来について、ポルトガル語の「チャラメラ(charamela)」に関係している。ポルトガルの「チャラメラ」も同様に楽器でオーボエの源流となったとも言われている。
日本に入ってきたのは16世紀で、当初は南蛮笛とも呼ばれていた。しかし、現在日本人がチャルメラと呼んでいる楽器は中国伝来の唐人笛「嗩吶(さない)(スルナイ)」のことである。
これについては江戸時代初期に長崎を訪れたポルトガル人が、嗩吶を見て自分の国の楽器に似ていたことから「チャラメラ」と呼んだことが原因だと言われている。
【実例・用例】
*歌謡・端唄部類〔1858〜65〕大つゑ畢「おこめほしさにナアナアみなとだよりてちゃらめららっぱ」
*大寺学校〔1927〕〈久保田万太郎〉一「露地の下で、飴屋、チャルメラをふきはじめる」
【漢字辞典】
「チャルメラ」の漢字表記は不明。