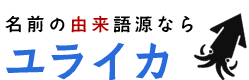【意味】
火薬を用い、摩擦によって火をつける道具。どこで摩擦しても火のつく摩擦マッチと、薬剤を軸木と箱とに分けて塗り、両者の摩擦で火のつく安全マッチとがある。
【名前の由来語源・成り立ち】
マッチの語源は、ラテン語がもとになっている。1800年代にイギリスの薬剤師が摩擦マッチを発明、ラテン語で「ロウソクの芯」を意味する「MYXA」という名前がつけられた。これが語源であり、ゆくゆき「MATCH」という言葉になり日本にも伝えられた。
日本で製造されるようになったのは明治八年(一八七五)で、地方にも普及したのは、同一五年以降といわれる。「早付木(はやつけぎ)」「摺付木(すりつけぎ)」などと訳されていたが、明治二〇年代に「燐寸」が現われ、これを「マッチ」と読む慣用が固定した。
【使い方・用例・実例】
*当世書生気質〔1885〜86〕〈坪内逍遙〉三「洋燧(マッチ)の空箱」
*不如帰〔1898〜99〕〈徳富蘆花〉上・一・二「燐寸(マッチ)を擦りて」
【漢字辞典】
「マッチ」を漢字で書くと「燐寸」と表記する。