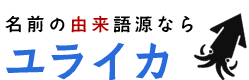【意味】
土筆(つくし)とは、スギナの胞子茎。円柱状で葉緑素を欠き淡褐色、節には黒褐色の鞘(さや)がある。早春、栄養茎に先だって地表にあらわれる。湯がいてあくを抜き、食用にする。つくづくし。つくしんぼう。つくしんぼ。
【名前の由来語源・成り立ち】
土筆(つくし)の名前の由来語源について、「つくづくし(土筆)」の省略形である。この「つくづくし」の語源は「突く」を重ねたものを言う。地上へ突き出すように伸びたさまをその名としたもの。「し」は接頭語である。
【使い方・用例・実例】
*自然と人生〔1900〕〈徳富蘆花〉湘南雑筆・彼岸「田の畔は土筆(ツクシ)、芹(せり)、薺(なずな)、嫁菜、野蒜(のびる)、蓬(よもぎ)なんど簇々として」
*俳句稿〈正岡子規〉明治三四年〔1901〕春「土筆煮て飯くふ夜の台所」
【漢字辞典】
「つくし」を漢字で書くと「土筆」「筆頭菜」と表記する。